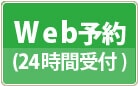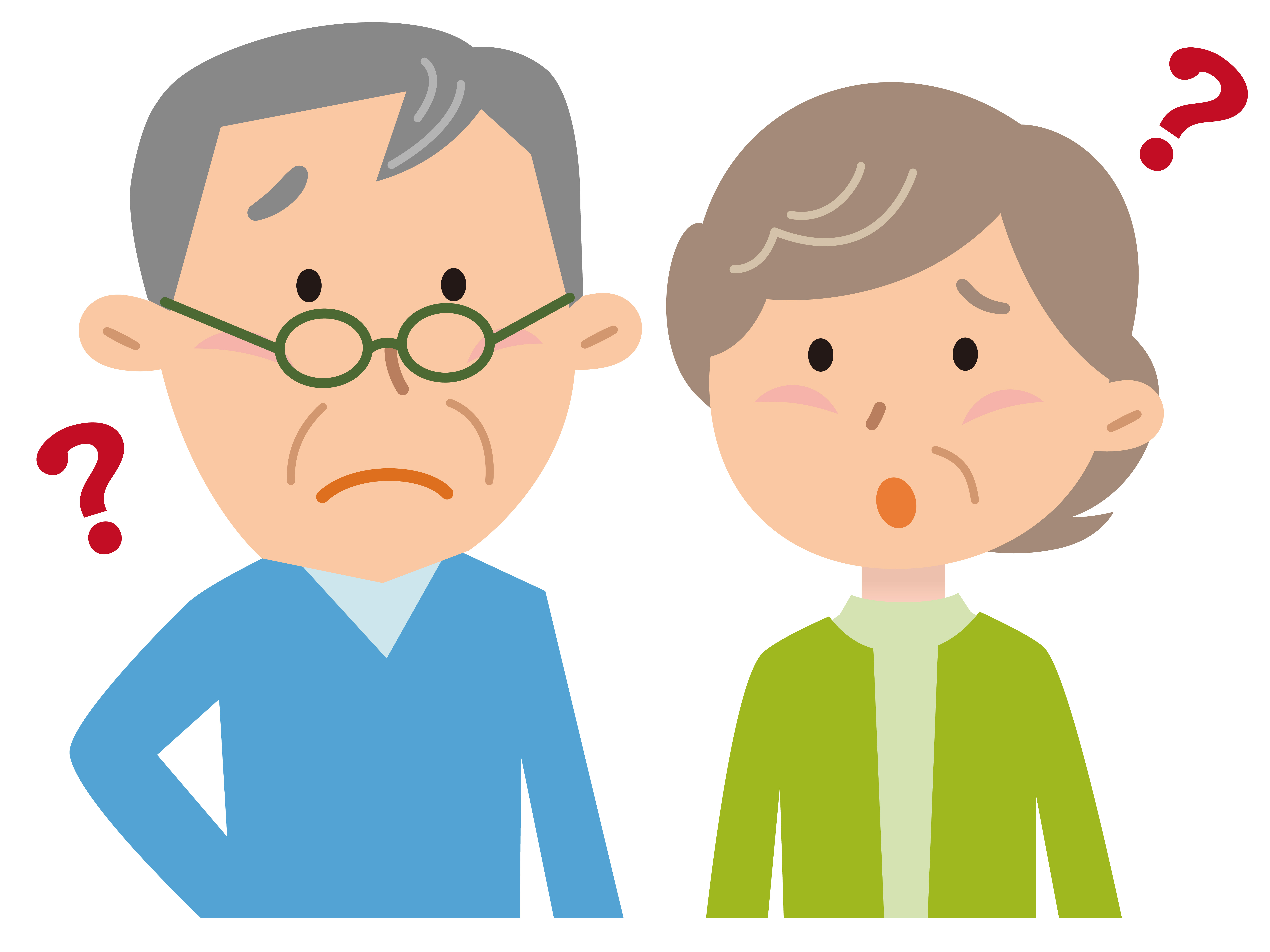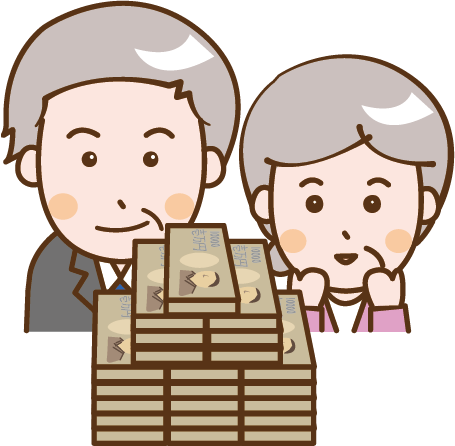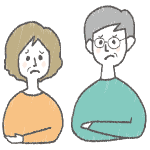年金分割の按分割合を50%以外にできますか?

実務上は困難です。
確かに、年金分割(合意分割)は制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能です。
そのため、当事者の合意で自由に決められるため、このような取り決めが容易であるかのような印象を受けられる方もいるかもしれません。
しかし、実務上は、50%以外の合意がなされることは非常に稀です。
なぜならば、按分割合で争いとなって、裁判上の手続きに移行した場合、裁判所では、ほとんど例外なく50%とするからです。
また、調停においても、50%が一般的であるという説明で、当然のようにそのようになります。
なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら請求者にあるような特段の事情がある場合は、若干の考慮要素になり得ますが、それでも実際には難しいと言わざるを得ません
年金分割のよくあるご相談
当事務所には、年金分割について、たくさんのご相談が寄せられています。
ここでは、現場の離婚弁護士が実際によく受けている年金分割の相談例をご紹介いたします。
①制度が理解できません
 インターネットなどで年金分割を調べると、説明が難しく理解できないという方が多くいらっしゃいます。
インターネットなどで年金分割を調べると、説明が難しく理解できないという方が多くいらっしゃいます。
そのため、年金分割について、「離婚の際に相手に年金を支払わなければならない」あるいは、「将来、相手に年金の半分を支払わなければならない」と勘違いをされている方もおられます。
しかし、そうではありません。年金分割とは、年金の支払い実績(記録)を分け与える制度です。
そのため、離婚時あるいは将来、相手に現金を支払わなければならないということはありません。
年金分割の結果、将来、年金を受給できる年齢になったとき、もらえる年金が減りますが、あくまで先の話となります。
②相手方との協議がまとまりません
離婚の場面では、年金分割以外にも決めなければならいことがたくさんあります。
例えば、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、親権などです。
また、離婚の場面では、通常、双方ともに相手方に悪感情を持っていることから、冷静な話し合いが難しいことが多くあります。
このような場合、当事者同士での解決は難しいと考えられます。
③ 年金分割(合意分割)の段取りは?
 年金分割の手続きに際しては、以下のような段取りが必要になります。
年金分割の手続きに際しては、以下のような段取りが必要になります。
「年金分割のための情報通知書」という書類を取得します。
![]()
協議等で分割割合を決めます。
![]()
その上で、合意について記載された文書を年金事務所に持参する(当事者双方または代理人)、
もしくは
合意内容を記載した公正証書または公証人の認証を受けた私署証書を作成して、年金事務所で手続きを行います。
年金分割を50%以外にする余地は?
前述のとおり、年金分割を50%以外にできる可能性は、実務上は困難といえます。
そのため、以下はそれでも50%以外にしたいという場合の、1つの参考程度にされてください。
説得材料を用意する
年金分割について、相手方に「50%は応じられない」と言っても、相手方は納得してくれないでしょう。
相手方に納得してもらうためには、「なぜ50%は不当なのか」ということを説得的に伝えなければならないでしょう。
そのためには、次のような主張が考えられます。
【所得の差が大きいこと】
夫側が高額な年金保険料を負担しており、妻側が扶養に入っていたため年金保険料をまったく負担していないなど
【長期間の別居があったこと】
別居してから長年月が経過しており、形式上の夫婦であったこと
ただし、上記の主張は、裁判においては認められない可能性が高いと思われます。
あくまで、説得の材料程度の意識のほうが良いでしょう。
公証役場の手続
年金分割は、公証役場において手続が可能です。
まず、年金分割の合意書を作成して、公証役場において、私文書の認証という手続をとることが一般的です。
素人の方には複雑で、やや難しいと思われます。
詳しい情報を次のページに掲載しているので、ぜひ、参考にされてください。
関連動画はこちら
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?